- 『風景の経験』J・アプルトン著 菅野弘久訳
- 『都市から見る世界史』J・コトキン著 庭田よう子訳
- 『宴のあとの経済学』E・F・シューマッハー著
- 『「フクシマ論」-原子力ムラはなぜ生まれたか』 開沼博著
- 『日本美の再発見』 ブルーノ・タウト著 篠田英雄訳
- 『国民総幸福度(GNH)による新しい世界へ』ジグミ・ティンレイ著 日本GNH学会編
- 『この最後の者にも』ジョン・ラスキン著 飯塚一郎訳
- 『都市のイメージ』ケヴィン・リンチ著 丹下/富田訳
- 『津波と原発』 佐野愼一著
- 『街並みの美学』『続・街並みの美学』 芦原義信著
- 『英国の未来像』 チャールズ皇太子著
- 『建築はほほえむ』 松山巖著
- 『ゆたかな社会』 ガルブレイス著
- 『荷風と明治の都市景観』 南明日香著
- 『英国の持続可能な地域づくり』 中島恵理著
- 『ブリューゲルへの旅』 中野孝次著
- 『世界まちづくり事典』 井上繁著
- 『なぜ日本は没落するか』 森嶋通夫著
- 『フランスの景観を読む-保存と規制の現代都市計画』 和田幸信著
- 『都市と人間』 陣内秀信著
- 『ドイツの地方都市はなぜ元気なのか-小さな街の輝くクオリティ』 高松平蔵著
- 『生活形式の民主主義-デンマーク社会の哲学』 ハル・コック著 小池直人訳
- 『人は愛するに足り、真心は信ずるに足りる-アフガンとの約束』 中村哲・聞き手:澤地久枝
- 『日本の景観 ふるさとの原型』 樋口忠彦著
- 『私の東京町歩き』
- 『創造都市への挑戦-産業と文化の息づく街へ』佐々木雅幸著
- 『都市の文化』1938年 ルイス・マンフォード著 生田勉訳 鹿島出版会1974年
- 『風景学-風景と景観をめぐる歴史と現在』中川理著 共立出版 2008年刊
- 『LRT-次世代型路面電車とまちづくり』宇都宮浄人/服部重敬著 成山堂書店刊
- 『富士山-聖と美の山』上垣外憲一著 中公新書2009年刊
- 『タテ社会の人間関係-単一社会の理論』中根千枝著 講談社現代新書初版1967年刊
- 『こころの詩-四季の彩り(はり絵画文集)』内田正泰画著 日貿出版社2011年刊
- 『人口減少社会という希望-コミュニティ経済と地球倫理』 広井良典著 朝日新聞出版 2013 年刊
- 『文化的景観-生活となりわいの物語』金田章裕著 日本経済新聞出版社2012年
- 『人間のための街路』バーナード・ルドフスキー著 鹿島出版会 原著初版1969年刊
- 『田端文士村』近藤富枝著 中公文庫 原著初版1975年刊
- 『はじめてわかるルネサンス』ジェリー・ブロトン著 ちくま学芸文庫 原著初版2006年刊
- 『茶色の朝』フランク・パヴロフ著 ギャロ絵 大月書店 原著初版2001年刊
- 『屋根』伊藤ていじ文・高井潔写真 淡交社 2004年刊
『都市から見る世界史』J・コトキン著 庭田よう子訳
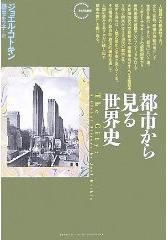
今回の東日本大震災では多くの都市が津波にのまれ、記憶に残らないぐらいの壊滅的状況を呈した。都市とは人々が生きてきたその生活の証であり臭いである。それをまったく灰燼に帰してしまうのが自然の力というものであろうか。しかし、人類が生息している限り都市は人類の歴史そのものとして現れる。
フランス人神学者J・エリュールが言ったように「自然の恩寵を失った人間が、その後新たに実現可能な秩序を創造しようとした試みが都市である」ということであろうか。 都市はその誕生当初から重要な三つの役割を担ってきたと著者はいう。即ち、神聖な場の創造、基本的安全の供給、商業取引の場である。そして、都市の研究によれば、「豊かな都市であっても道徳的な絆や市民としてのアイデンティティが欠ければ、退廃的になり衰退する運命が待っている」という。
著者は人類の歴史を都市の観点から見てゆく。先ず、都市の起源を問い、古代ギリシア・ローマの事例を挙げ、東洋に飛びイスラーム・中華帝国の都市を論じ、ヨーロッパ都市がどのように出来上がり、近代化の足音がする工業都市の出現、そして人類が良い都市を求めるという事はどういうことであるかを問い、最後に都市の未来を論じて終わる。著者は「人類最大の創造物は、いつの時代でも都市だった。
都市は人類の想像力の究極の作品であり、大きな意味を持ち、奥深く、しかも耐久性のある方法で自然環境を再構成する能力の証である」を基本にしている。 確かに、都市とはそこに住む市民が共通のアイデンティティで結び付いていてこそ生きた都市である。人類の長い都市の歴史を振り返り、「都市は大衆の複雑な性質をまとめ、活気を与える役割を果たす神聖な場所を支配することによってのみ栄えることができる」との著者の結論には、まさに現代人が失ってしまった「場の神聖性」を呼びかけているのである。(斉藤全彦)